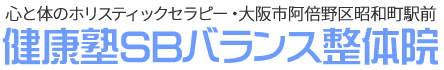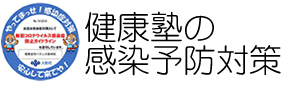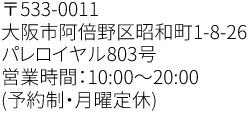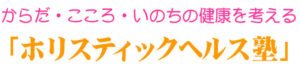“誰かのため”が自分を癒す:ケアと助け合いの循環
「誰かの力になりたい」
「少しでも役に立ちたい」
「この人に、何かしてあげたい」
そんなふうに思った瞬間、
自分の中に静かに力が湧いてくる感覚を、あなたも感じたことがあるのではないでしょうか。
実はこの「誰かをケアする」という行為そのものに、
私たち自身を癒す力があると、ホリスティックヘルスでは考えられています。
与えることで満たされる、という本能
家族の世話をするとき
友人に寄り添うとき
困っている誰かに手を差し伸べたとき
「自分が誰かの力になれた」と実感できる瞬間、
心の奥からじんわりとあたたかさが広がり、
自己肯定感が育まれるのを感じることがあります。
ここには、人間が本来持っている「与えることで満たされる」という、
とても自然な本能が働いています。
ケアと犠牲は、違うもの
ただし、大切なポイントがあります。
それは、「ケア」と「自己犠牲」は違うということ。
-
「私さえ我慢すれば」
-
「自分のことは後回しでいい」
-
「疲れていても、無理してでもやらなきゃ」
そんなふうに、自分を置き去りにしてしまうと、
ケアはやがて“疲れ”や“消耗”につながってしまいます。
ホリスティックなケアとは、
「自分も、相手も、どちらも大切にすること」。
つまり、自分の心に余裕があるときに、その一部を差し出すというイメージです。
自分を満たしてから、分かち合う
たとえば、誰かの話を聴く前に、まずは深呼吸をして、自分の緊張をゆるめる。
忙しい日でも、5分だけ一人になって心を整えてから、家族と向き合う。
それだけでも、ケアの質がまったく変わってきます。
自分のエネルギーを満たした状態で誰かに向き合うと、
その関わりは、押しつけではなく、自然な“分かち合い”になります。
「受け取る力」も、循環の一部
もうひとつ、忘れてはならないのが「受け取る力」。
ケアや思いやりが“循環”するためには、受け取ることもとても大切です。
-
誰かの親切に「ありがとう」と素直に言う
-
困ったときに「助けて」と伝える
-
何かをしてもらったとき、申し訳なさよりも感謝を感じる
このように“受け取ること”もまた、私たちのセルフケアの一部です。
ケアは「支え合い」のなかで育つ
助け合いとは、一方的な奉仕ではなく、
**エネルギーの行き来がある“あたたかな循環”**です。
-
誰かに必要とされると、自分の存在に意味を感じられる
-
誰かに頼ることができると、自分は「ひとりじゃない」と実感できる
この両方があるからこそ、私たちは安心して生きていけるのです。
小さな循環を、日常の中に
では、私たちが今すぐできる“循環”とは、どんなことでしょうか?
-
朝、家族に「おはよう」と優しく声をかける
-
同僚に「ありがとう」と一言伝える
-
SNSで、誰かの投稿に共感を示す
-
街で困っている人に、そっと声をかける
どれもほんの小さな行動ですが、
その積み重ねが、社会全体の空気をやわらかく、あたたかくしていきます。
“誰かのため”が、“自分のため”になる
最後に、心にとめておきたいこと。
誰かのためにした行動が、自分の心を癒すことがあるということです。
-
誰かの笑顔を見ることで、自分の心もほっとする
-
誰かの痛みに寄り添うことで、自分の中の傷も少し癒える
人と人とが深いところでつながるとき、
そのつながりは、両方の心をやさしく包んでくれるのです。
今日、あなたが始められる小さなケアは?
この記事を読んだあと、少し立ち止まって、自分に問いかけてみてください。
-
私は、どんなふうに人と関わっていきたいだろう?
-
私が誰かに届けられる、小さなケアは何だろう?
-
そして、誰にどんなふうに助けてもらいたい?
助け合いの循環が広がっていくとき、
世界はもっとあたたかく、呼吸のしやすい場所になっていく。
その始まりは、
今日のあなたの小さな選択からかもしれません。