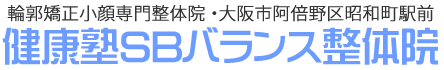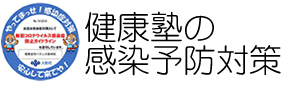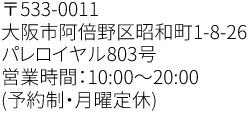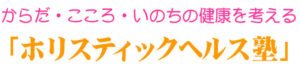私は顎先が左に流れています。これは改善しますか?
ご質問ありがとうございます。顎先が左右どちらかに流れて見える、または動くというお悩みは非常に多くの方が抱えていらっしゃいます。結論から申し上げますと、適切なアプローチによって十分に改善が見込めます。
顎先の歪みは、単に顎だけの問題ではなく、顎関節(科学骨)のズレと全身のバランスの乱れが大きく影響しています。その原因と、当院での改善アプローチについて詳しく解説します。
顎先が流れる主な原因:骨格の機能的問題と生活習慣
顎先の歪みは、大きく分けて「構造的な機能の問題」と「日常の習慣」の2つの側面から考える必要があります。
1. 顎関節の機能的な問題(骨の変形ではない)
顎先の流れは、下顎骨自体の変形(奇形や事故など)ではなく、ほとんどの場合、顎関節の左右不一致、つまり機能的な問題によって起こっています。顎関節は非常に複雑な動きをする関節です。
- 軸関節と転がり運動: 顎関節は、口の開口時、軸関節としての動きと、そこから更に大きく開ける時の転がり運動を組み合わせた複雑な動きをします。
- 軟部組織の関与: 関節は、靭帯や筋肉、そして衝撃を吸収する関節円盤という軟骨組織によって支えられています。これらの軟部組織の緊張や緩みが原因で、顎がスムーズに動かず、顎先が流れてしまうことがあります。
厳密に言うと、人間の体は完全に左右対称ではありませんが、今回は形(骨自体の問題)の歪みというより、関節の機能的な問題として捉え、改善を目指します。
2. 日常の生活習慣による持続的な圧迫(これが最大の原因)
顎関節がずれる原因として、日常生活の無意識の癖が非常に大きな割合を占めます。顎の骨(下顎骨)は動きやすい骨であるため、継続的な外力が加わると歪みやすいのです。
特に、顎先が左右に流れる歪みを生む代表的な癖は以下の2つです。
① 頬杖(ほおづえ)による持続的な圧迫
- 頬杖をつくことで、下顎骨の一点に継続的に強い力が加わり、顎関節が押されてズレることが非常に多いです。
- せっかく調整しても、この癖を止めなければ元に戻ってしまうため、整体での調整と同時に、頬杖をやめていただくことが非常に重要です。
② 片側噛み(偏咀嚼)による筋肉バランスの崩れ
- 片側だけで硬いものや柔らかいものを噛み続けると、そちら側の顎関節が下がり気味になり、結果的に顎先が反対側へ流れる原因になります。
この他、うつぶせ寝などの寝る姿勢も顎関節に持続的な歪みを生む原因となります。
改善へのアプローチ:整体院の視点
当院では、顎先の流れを改善するために、以下のステップでアプローチしていきます。
ステップ1:原因特定の評価(カウンセリング)
輪郭矯正や小顔矯正、腰痛など、体の不調には必ず原因があります。初回のカウンセリングでは、まず顎先の流れの原因が、上記のどのパターンに該当するかを丁寧に評価・検査します。
- 機能の検査: 顎関節の開口時の動き、左右への動き、靭帯・筋肉の状態。
- 全身の連動検査: 顎だけでなく、土台となる骨盤や背骨、頸椎の歪みをチェックし、顎の歪みが全身の代償として出ていないかを確認します。
ステップ2:根本原因に対する調整(施術)
顎関節自体はもちろんですが、全身のバランスを整えることで、顎関節にかかっている余計な負担を取り除きます。
- 関節調整: 顎関節の転がり運動をサポートし、左右不一致となっている関節円盤や靭帯、筋肉を最適な状態に導くための調整を行います。
- 全身の土台調整: 顎関節の歪みの原因となっている骨盤や背骨の歪みを整え、頭が安定して乗る土台を作ります。
ステップ3:再発防止のための生活習慣の改善
せっかく施術で調整しても、原因となる生活習慣(頬杖や片噛みなど)を改善しなければ、元の状態に戻ってしまいます。
私たちは、患者様ご自身が原因となる習慣を認識し、日常的な範囲で改善できるようサポートします。その原因をなるべく意識的にやらないように努めていただくことが、この顎の流れを十分改善していくための鍵となります。
はい、ありがとうございます。
動画では歪みの原因も解説しています。